日常生活で「1リットルって何キロなの?」と疑問に思ったことはありませんか。料理でレシピを見るとき、スーパーで買い物をするとき、この疑問は意外と頻繁に浮かんでくるものです。
結論から申し上げますと、水1リットルの重さは1キログラムです。ただし、牛乳や油など液体によって重さは変わります。
この記事では、日常でよく使う液体の1リットルあたりの重さを一覧表でご紹介し、料理や買い物で役立つ活用方法、そして「なぜ液体によって重さが違うのか」という疑問まで、分かりやすく解説いたします。この知識があれば、毎日の生活がちょっと便利になりますよ。
【結論】1リットルの重さ一覧表|水1kg、牛乳1.03kg
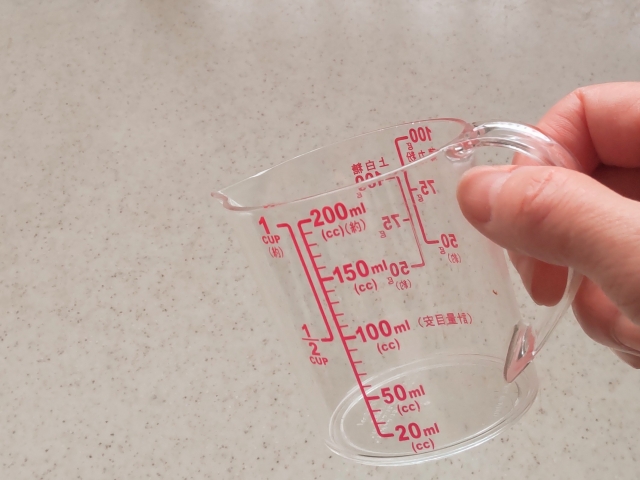
まずは結論から。日常生活でよく使う液体を中心に、1リットルあたりの重さを一覧表にまとめました。料理や買い物の際に、ぜひ手元に置いて参考にしてください。
日常でよく使う液体
| 液体名 | 1リットルあたりの重さ |
|---|---|
| 水 | 1.00kg |
| 牛乳 | 1.03kg |
| 食用油(サラダ油など) | 0.92kg |
| 醤油 | 1.15kg |
| みりん | 1.20kg |
| 料理酒 | 1.05kg |
| 酢 | 1.02kg |
その他の液体
| 液体名 | 1リットルあたりの重さ |
|---|---|
| オレンジジュース | 1.04kg |
| コーラ | 1.04kg |
| ビール | 1.01kg |
| ガソリン | 0.75kg |
| 灯油 | 0.80kg |
| エタノール(アルコール) | 0.79kg |
この表を見ると、水を基準として、醤油やみりんは水より重く、油類は水より軽いことが分かります。なぜこのような違いが生まれるのかは、後ほど詳しく解説いたします。
水1リットルが1キログラムである理由

多くの液体の中で、なぜ水だけが「1リットル=1キログラム」という、きれいで覚えやすい数値になるのでしょうか。実はこれには、重さの単位である「キログラム」が生まれた歴史が深く関係しています。
キログラムの定義と水の深い関係
現在でこそキログラムの定義は複雑な物理定数(プランク定数)に基づいていますが、1889年から2019年まで長い間、キログラムは「国際キログラム原器」という金属の塊の重さで定義されていました。
キログラムの定義の歴史をさかのぼると、1799年に最初に作られたキログラム原器は「摂氏4度の水1立方デシメートル(1リットル)の質量」を基準として作られました。その後1889年に現在の国際キログラム原器が定められましたが、この重さも元をたどれば水の重さが基準となっています。
つまり、「水1リットル=1キログラム」となるのは、ある意味当然の結果だったというわけです。
水の密度について
水の密度は摂氏4度で最大となり、その値は約0.99997g/cm³(実用上は1g/cm³として扱います)です。これを分かりやすく表現すると:
- 1cm × 1cm × 1cm の立方体の水の重さ = 1g
- 10cm × 10cm × 10cm の立方体の水の重さ = 1000g = 1kg
- 10cm × 10cm × 10cm = 1000cm³ = 1リットル
このように、水の密度が1g/cm³であることから、自然に「水1リットル=1kg」という関係が成り立ちます。
温度による微妙な変化
実は、水の重さは温度によって微妙に変化します。水は摂氏4度のときに最も密度が高くなり、温度が上がるにつれて少しずつ軽くなります。
- 4℃の水:1.000kg/L
- 20℃の水:0.998kg/L
- 60℃の水:0.983kg/L
ただし、日常生活ではこの差はほとんど気にする必要がありません。料理や買い物の場面では「水1リットル=1kg」として計算して問題ありません。
料理・買い物で使える!1リットル何キロの活用法
1リットルあたりの重さを知っていると、日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ここでは、特に便利な料理と買い物での具体的な活用シーンをご紹介します。
料理での活用シーン
レシピの分量換算
料理のレシピで「牛乳200ml」と書かれているとき、キッチンスケールしかない場合の換算に役立ちます。
計算例:牛乳200mlは何グラム?
– 牛乳の重さ:1.03kg/L = 1.03g/ml
– 200ml × 1.03g/ml = 206g
このように、約206gを計量すればよいことが分かります。
計量カップとキッチンスケールの使い分け
- 水や牛乳:計量カップでもキッチンスケールでも大きな差なし
- 油類:水より軽いため、100mlの油は100gより軽い(約92g)
- 醤油やみりん:水より重いため、100mlは100gより重い
この特性を知っていれば、手持ちの計量器具に応じて臨機応変に対応できます。
大量調理の際の重量計算
学校行事や地域イベントなどで大量調理をする際、事前に重量を把握しておくことで、買い物計画や運搬計画が立てやすくなります。
例:100人分のカレーを作る場合
– 水20L = 20kg
– 牛乳5L = 約5.15kg
– 醤油2L = 約2.3kg
買い物での活用シーン
重い買い物の事前計算
スーパーで液体を大量に買う前に、重さを予想しておけば持ち帰りの負担が分かります。
具体例:調味料をまとめ買いする場合
– 醤油1L × 3本 = 約3.45kg
– みりん1L × 2本 = 約2.4kg
– 料理酒1L × 2本 = 約2.1kg
– 合計:約7.95kg
この重さが分かっていれば、車で行くか、配送サービスを利用するかの判断ができます。
災害時の備蓄計画
災害時の水の備蓄を考える際にも、この知識は役立ちます。
例:家族4人×3日分の飲料水
– 必要水量:約36L(1人1日3L × 4人 × 3日)
– 重量:約36kg
2Lペットボトルなら18本で36kgとなり、保管場所や運搬方法を事前に検討できます。
液体によって重さが違う理由|密度の基礎知識

水と油で重さが違うように、同じ1リットルでも液体によって重さが異なるのはなぜでしょうか。そのカギを握るのが「密度」という考え方です。ここでは密度の基本を分かりやすく解説します。
密度とは何か
密度とは、「決まった体積の中にどれだけの物質が詰まっているか」を表す値です。
身近な例で説明すると:
- スポンジ:同じ大きさでも軽い(密度が小さい)
- 鉄の塊:同じ大きさでも重い(密度が大きい)
液体でも同じことが起こります。同じ1リットルでも、中に詰まっている分子の種類や密度によって重さが変わるのです。
なぜ液体によって密度が違うのか
液体の密度は、主に以下の要因で決まります:
分子の重さ
- 水:軽い分子(H₂O)
- 醤油:塩分やアミノ酸など重い成分が溶けている
分子の詰まり具合
- アルコール:分子同士の隙間が大きい
- 砂糖水:砂糖分子が水分子の隙間に入り込む
溶けている物質
- 牛乳:タンパク質や脂肪が溶けている
- 醤油:塩分や有機酸が高濃度で溶けている
身近な例:水と油、氷が浮く理由
水と油が分離する理由
油の密度(約0.92g/cm³)が水の密度(1.0g/cm³)より小さいため、油は水に浮きます。これは、油の分子構造が水より軽いためです。
氷が水に浮く理由
実は、氷の密度(約0.92g/cm³)は液体の水より小さくなります。これは、水が凍るときに分子が規則正しく並んで隙間ができるためです。この珍しい性質により、湖が凍っても氷が表面に浮き、魚が生きていけるのです。
1リットルから重さを計算する方法

一覧表にない液体の重さを知りたいときや、もっと正確な重さを計算したいときのために、自分で計算する方法を覚えておくと便利です。基本の計算式と具体例を見ていきましょう。
基本の計算式
体積(L) × 密度(g/cm³) × 1000 = 重さ(g)
なぜ1000をかけるかというと:
- 1L = 1000cm³
- 密度がg/cm³で表されているため
- 単位を合わせるために1000倍する必要がある
具体的な計算例
例1:食用油500mlの重さ
- 食用油の密度:0.92g/cm³
- 500ml = 0.5L
- 計算:0.5L × 0.92g/cm³ × 1000 = 460g
例2:醤油2Lの重さ
- 醤油の密度:1.15g/cm³
- 計算:2L × 1.15g/cm³ × 1000 = 2300g = 2.3kg
例3:みりん300mlの重さ
- みりんの密度:1.20g/cm³
- 300ml = 0.3L
- 計算:0.3L × 1.20g/cm³ × 1000 = 360g
密度の調べ方
各液体の密度は、以下の方法で調べることができます:
- 食品表示ラベル:一部の商品に記載されている場合がある
- メーカーの公式サイト:技術仕様として公開している場合がある
- 理科の資料集:基本的な液体の密度が掲載されている
- インターネット検索:「○○ 密度」で検索
ただし、同じ種類の液体でも製品によって微妙に密度が異なる場合があるため、正確性が重要な場面では実測をおすすめします。
知っておいて損なし!液体の重さ豆知識

ここでは、日常の会話や雑学として知っておくと面白い、液体の重さに関する豆知識をいくつかご紹介します。
最も軽い液体・重い液体
身近な液体で最も軽いもの:液体ヘリウム
– 密度:約0.125g/cm³(-269℃)
– 1リットルでわずか125g
身近な液体で最も重いもの:水銀
– 密度:約13.6g/cm³
– 1リットルで13.6kg(水の13.6倍!)
季節で変わる液体の重さ
実は、同じ液体でも季節(温度)によって重さが微妙に変わります:
ガソリンの例
– 夏場(30℃):約0.740kg/L
– 冬場(0℃):約0.765kg/L
ガソリンスタンドの計量は体積で行われるため、厳密には同じ値段でも冬の方が少し重いガソリンを購入していることになります。
料理の世界の密度活用法
卵の新鮮度チェック
新鮮な卵は密度が高く水に沈み、古い卵は密度が下がって水に浮きます。これは、卵の中の水分が蒸発して空気が入るためです。
お酒の度数と密度
アルコール度数が高いお酒ほど密度が低くなります。これを利用して、昔の人は比重計でお酒の度数を測っていました。
よくある質問|1リットル何キロについて

最後に、「1リットルと重さ」に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。より深く理解するための参考にしてください。
Q:計算結果と実測値が違うのはなぜ?
A:以下の理由が考えられます:
- 温度の違い:密度の基準温度と実際の温度が異なる
- 成分のばらつき:同じ商品でも製造ロットにより微妙に成分が異なる
- 計量器具の誤差:スケールや計量カップの精度による誤差
- 空気の混入:液体に微細な泡が混じっている
日常使いでは1~2%程度の誤差は正常範囲内と考えてください。
Q:同じ牛乳でもメーカーによって重さは違う?
A:はい、微妙に違います。
- 乳脂肪分の違い:3.5%と4.0%では密度が異なる
- 無脂乳固形分の違い:メーカーごとに成分規格が微妙に異なる
- 製造方法の違い:均質化の程度により密度が変わる場合がある
ただし、違いは通常1~2%程度で、日常生活ではほとんど気にする必要がありません。
Q:温度で重さは変わる?
A:はい、変わりますが日常生活ではほぼ無視できる程度です。
水の例:20℃→80℃に温めた場合
– 20℃:0.998kg/L
– 80℃:0.972kg/L
– 差:約2.6%
料理や一般的な計量では、この差を考慮する必要はありません。ただし、精密な実験や工業用途では温度補正が必要な場合があります。
まとめ|1リットルの重さを覚えて生活に活用しよう

この記事では、「1リットルは何キロ?」という疑問について詳しく解説してきました。
重要なポイント
- 水1リットル = 1キログラムが基本の基準
- 液体によって重さは異なる(密度の違いによる)
- 計算方法は簡単:体積 × 密度 = 重さ
- 日常生活で活用できる場面は多い
覚えておきたい重さ一覧(再掲)
- 水:1.00kg/L
- 牛乳:1.03kg/L
- 食用油:0.92kg/L
- 醤油:1.15kg/L
- みりん:1.20kg/L
実生活での活用メリット
- 料理:計量がスムーズになる
- 買い物:持ち帰り重量の事前計算ができる
- 備蓄計画:必要な保管スペースが計算できる
- 節約:効率的な買い物計画が立てられる
これらの知識を活用すれば、毎日の生活がちょっと便利になります。特に、料理好きの方や大家族の方、災害対策を考えている方には、きっと役立つ知識となるでしょう。
「1リットルは何キロ?」という疑問から始まって、密度の概念や実用的な活用法まで、幅広い知識を身につけることができました。今度スーパーで買い物をするときや料理をするときに、ぜひこの知識を思い出してみてくださいね。

