「手元に青い絵の具がないけど、青色を作りたい」「お菓子作りに使う青い食紅は作れるの?」「パソコンで理想の青を表現したい」
このような疑問や悩みを抱えていませんか?一口に「青色を作る」と言っても、その方法は使用する材料や目的によって大きく異なります。この記事では、絵の具の混色といった基本的なテクニックから、食紅を使った安全な着色方法、デジタルでの色彩表現、さらには藍染に代表される伝統的な自然染料まで、青色を作るためのあらゆる方法を徹底的に解説します。初心者の方でもすぐに実践できるよう、具体的な手順や成功のコツも詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
青色作りの基本知識

あらゆる「青作り」を始める前に、まずは色の基本原理について理解を深めましょう。なぜ青は特別なのか、その理由を知ることで、各手法への理解度が格段に上がります。
色の三原色について
青色を作る方法を理解する上で欠かせないのが、「色の三原色」の知識です。色は、光が合わさって色を生み出す「光の三原色」と、色材が混ざって色を生み出す「色材の三原色」の2つの原理に基づいています。
- 光の三原色(加法混色)
- 赤(Red)
- 緑(Green)
- 青(Blue)
テレビやスマートフォンの画面は、この3色の光の組み合わせで様々な色を表現しています。色を混ぜるほど明るくなり、3色を最大で混ぜると白になります。
- 色材の三原色(減法混色)
- シアン(Cyan / 青緑)
- マゼンタ(Magenta / 赤紫)
- イエロー(Yellow / 黄)
絵の具や印刷インクなどがこの原理に基づいています。色を混ぜるほど光の吸収率が高まり、暗くなります。理論上、3色を混ぜると黒になります。私たちが「青色を作る」と考える時の青色は、厳密にはこの色材の三原色におけるシアンに近い色を指すことが多いのです。
なぜ青色は作りにくいのか
結論から言うと、色材の三原色であるシアン、マゼンタ、イエローは、他の色を混ぜ合わせて作り出すことができない「原色」です。そのため、厳密な意味での「青色(シアン)」を他の色から作り出すことは原理的に不可能です。これは青色に限らず、赤色(マゼンタ)や黄色(イエロー)も同様です。
しかし、これはあくまで理論上の話です。私たちが普段「青」と認識している色には、空色、紺色、群青色など無数のバリエーションが存在します。これらの「青系の色」であれば、色の三原色をベースに他の色を混ぜ合わせることで、作り出すことが可能です。この記事では、この「青系の色を作り出す方法」を様々な角度から探求していきます。
絵の具での青色の作り方

学校の美術の授業や趣味の絵画で、最も身近な青作りといえば絵の具でしょう。ここでは、手持ちの絵の具で理想の青に近づけるための基本的な考え方から、具体的な混色テクニックまでを詳しく解説します。
基本的な考え方
前述の通り、純粋な青(シアン)を他の色から作り出すことはできません。市販の絵の具セットに入っている基本的な色(赤・黄・緑など)だけでは、鮮やかな青を作るのは非常に困難です。しかし、完全に不可能というわけではありません。色材の三原色に近い色を持っていれば、青に近い色を作り出すことができます。
シアンとマゼンタを使用する方法
最も純粋な青に近い色を作る方法は、色材の三原色である「シアン」と「マゼンタ」を使うことです。この2色があれば、紫がかったロイヤルブルーから深みのある青まで、様々な青色を表現できます。
必要な材料:
- シアン(青緑)の絵の具
- マゼンタ(赤紫)の絵の具
作り方:
- パレットにシアンを基本の色として出します。
- そこに、ごく少量のマゼンタを筆の先で加えます。まずはシアン8:マゼンタ2程度の比率から試してみましょう。
- よく混ぜ合わせ、色味を確認します。マゼンタを少しずつ足していくことで、シアンの緑っぽさが消え、深みのある青色に変化していきます。
- 理想の青色になるまで、焦らず少しずつ調整するのがコツです。
代用色を使った青色作り
手元にシアンやマゼンタがない場合でも、他の色を組み合わせて青系の色を作ることは可能です。ただし、これらの方法はあくまで代用であり、純粋な青ではなく、やや彩度が低く、くすんだ色合いになることを覚えておきましょう。
代用色での組み合わせ例:
- 紫 + 緑(少量):紫をベースに、ほんの少し緑を加えることで、紺色のような暗い青系の色を作れます。緑が多すぎると濁るので注意が必要です。
- 水色 + 紺色:既存の青系2色を混ぜる方法です。水色に紺色を少しずつ加えることで、中間の明るさの青を作ることができます。
- ターコイズブルー + 紫(微量):ターコイズブルーの黄みや緑みを、補色に近い紫を少量加えることで打ち消し、より純粋な青に近づけるテクニックです。
絵の具の種類別の特徴
使用する絵の具の種類によっても、青色の表現方法は変わってきます。
- 透明水彩での青色作り
透明水彩の魅力は、その名の通り「透明感」です。水の量を調節することで、淡い空色から深い海の底のような色まで、無限の青のグラデーションを表現できます。特に、ウルトラマリンやコバルトブルーといった顔料は、その美しさから多くの画家に愛されています。 - 不透明水彩(ガッシュ)やアクリル絵の具での青色作り
不透明な絵の具は、下の色を隠す力が強い(隠蔽力が高い)ため、混色が直感的で分かりやすいのが特徴です。白を混ぜて明度を上げたり、黒を混ぜて暗くしたりと、色相・明度・彩度を自由にコントロールして思い通りの青色を作りやすいでしょう。
青色のバリエーションを作る方法
基本の青色が作れたら、白や黒、その他の色を混ぜて様々な青色のバリエーションを生み出してみましょう。
- 水色の作り方:青 + 白(多め)。基本の青に白を少しずつ加えて、理想の淡さになるまで調整します。
- 紺色の作り方:青 + 黒(少量)。青4~5に対して黒1程度を目安に混ぜ、色味を見ながら微調整します。黒を入れすぎるとただの暗い色になってしまうので注意が必要です。
- 群青色の作り方:青 + 赤紫(マゼンタに近い色)。基本の青に、赤紫を少量加えることで、紫がかった深みのある群青色になります。
- ターコイズブルーの作り方:青 + 緑。青をメインに、緑を少しずつ混ぜていくと、南国の海のような美しいターコイズブルーが作れます。
混色の注意点とコツ
美しい青を作るためには、いくつかの重要なポイントがあります。
- 少しずつ加える:色は一度混ぜてしまうと元に戻せません。特に濃い色や暗い色は、ごく少量ずつ加えて慎重に調整しましょう。
- 明るい色から混ぜる:濃く暗い色を薄く明るい色に変えることは困難です。パレットの上では、薄く明るい色に、それより濃い色や暗い色を混ぜていくのが基本です。
- 筆やパレットを清潔に保つ:混色を繰り返すと、意図しない色が混ざり、色が濁る原因になります。特に、補色関係にある黄色などが混ざると、青の鮮やかさが著しく失われます。色を変えるたびに筆をきれいに洗い、パレットも整理整頓を心がけましょう。
食紅での青色の作り方

お菓子作りや料理で、美しい青色を表現したい場面もあります。ここでは、食紅を使って安全に青色を作る方法や、手元にない場合の代用品について解説します。
食紅で青色は作れるのか
絵の具と同様に、食紅でも他の色を混ぜて青色を作ることはできません。市販されている食紅の基本セットは赤・黄・緑が一般的で、これらを混ぜ合わせても青や黒は作れません。青色を表現したい場合は、青色の食紅を別途購入する必要があります。
市販の青い食紅を使用する
最も手軽で確実な方法は、市販の青い食用色素(食紅)を使用することです。以前は手に入りにくい品目でしたが、現在は製菓材料店やオンラインショップなどで比較的簡単に見つけることができます。
主な青色食紅の種類:
- 天然由来:クチナシ青色素(ガーデニアブルー)
クチナシの果実から抽出される天然の色素です。穏やかで自然な青色に染まりますが、熱や光にやや弱い性質があります。 - 合成着色料:食用色素青色1号(ブリリアントブルーFCF)
化学的に合成された色素で、非常に鮮やかな青色が出ます。少量でくっきりと着色でき、熱や光にも強いのが特徴です。
どちらを選ぶかは、作りたいもののイメージや、添加物に対する考え方によって決めると良いでしょう。
天然の代用品で青色を作る
青い食紅が手に入らない場合や、より自然な材料を使いたい場合は、身近な食材で青色を作り出すことも可能です。
紫キャベツを使った方法
理科の実験としても有名な方法です。紫キャベツに含まれるアントシアニンという色素は、アルカリ性の物質に反応して青色に変化する性質を持っています。これを利用して、安全な青い着色料を作ることができます。
手順:
- 紫キャベツを細かく刻みます。
- 鍋にキャベツとひたひたの水を入れ、煮出して紫色の汁を作ります。
- できた煮汁に、食用の重曹(ベーキングソーダ)をごく少量ずつ加えます。
- すると、不思議なことに紫色の液体が鮮やかな青色に変化します。
この液体は、ゼリーや飲み物の色付けに使えます。ただし、重曹を入れすぎると苦味が出るので注意してください。
その他の天然材料
他にも、青系の色を持つ天然の食材を利用する方法があります。
- ブルーベリー:ブルーベリーを潰して絞った汁は、美しい青紫色の着色料になります。ヨーグルトやスムージーの色付けに最適です。
- バタフライピー:タイなどで有名なハーブティー。乾燥した花にお湯を注ぐと鮮やかな青いお茶になります。レモン汁など酸性のものを加えると紫色に変化する特性も楽しめます。
食紅を使う際の注意点
食紅を使って生地やクリームに着色する際には、ちょっとしたコツが必要です。
- 生クリームに着色する場合:
食紅は必ず生クリームを泡立てる「前」に加えてください。泡立てた後に食紅を加えると、色を均一に混ぜようとするうちにクリームを混ぜすぎてしまい、分離してボソボソになる原因となります。 - チョコレートに着色する場合:
通常の水溶性の食紅は、油分であるチョコレートにはうまく混ざりません。油性の食用色素を使用するか、粉末の食紅に少量のサラダ油などを混ぜてペースト状にしたものを、溶かしたホワイトチョコレートに加えてください。
デジタルでの青色の作り方

Webサイトやデザイン、イラストなど、デジタル環境で色を扱う場合、青色の作り方は物理的な混色とは全く異なるアプローチになります。ここではRGBとCMYKという2つの主要なカラーモデルについて解説します。
RGBカラーモデルでの青色
パソコンのモニターやスマートフォンのディスプレイは、RGB(Red, Green, Blue)の「光の三原色」で色を表現しています。それぞれの色の光を0から255の数値で組み合わせることで、約1677万もの色を作り出します。
基本的な青色のRGB値:
- 純粋な青:R:0, G:0, B:255
- 空色(スカイブルー):R:135, G:206, B:235
- 濃紺(ネイビーブルー):R:0, G:0, B:128
青色のバリエーション作成:
- 明るい青:Bの値を高く保ちつつ、RやGの値を少し加えることで、彩度を保ったまま明るい青になります。
- 深い青:Bの値を高くし、RやGの値を微量加えることで、黒を混ぜるのとは違う、深みのある青が作れます。
- 青緑(シアン):Bの値とGの値を高くすることで、鮮やかなシアンになります。(例: R:0, G:255, B:255)
CMYKカラーモデルでの青色
ポスターや雑誌、パンフレットなどの印刷物を作成する場合は、CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Key plate=Black)の「色材の三原色」に基づいたカラーモデルを使用します。こちらはインクの量を0から100%で表現します。
基本的な青色のCMYK値:
- 純粋な青(ロイヤルブルー):C:100, M:70, Y:0, K:0
- 空色(スカイブルー):C:60, M:10, Y:0, K:0
- 濃紺(ネイビーブルー):C:100, M:90, Y:0, K:40
RGBからCMYKへの変換時の注意点
ここで非常に重要なのが、RGBとCMYKでは表現できる色の範囲(色域)が異なるという点です。一般的に、光で表現するRGBの方が色域が広く、特に鮮やかな青、緑、ピンクなどは、インクで表現するCMYKでは再現しきれずに色がくすんでしまいます。
Webサイト用にRGBで作った鮮やかな青色のロゴを、そのまま印刷用のデータに変換すると、想像していたよりもずっと暗く、濁った色合いで印刷されてしまうことがあります。そのため、印刷物を作成する際は、最初からCMYKカラーモードで作業するか、変換時の色味の変化を十分に想定しておく必要があります。
色のくすみを抑える方法:
専門的なテクニックになりますが、Photoshopなどの画像編集ソフトで、一度RGBから「Labカラー」という別のカラーモデルに変換し、明るさや彩度を調整してからCMYKに再変換すると、くすみをある程度抑制できる場合があります。
自然染料・藍染での青色の作り方

化学染料が生まれる遥か昔から、人々は植物を使って布を染めてきました。その中でも「青」を染める代表的な方法が「藍染」です。ここでは、日本の伝統文化でもある藍染の世界をご紹介します。
藍染の基本
藍染とは、タデ科の「藍」という植物に含まれるインディゴという色素を利用して染める技法のことです。その歴史は古く、世界中で行われてきました。日本では特に江戸時代に庶民の間で広まり、衣類から暖簾、手ぬぐいまで、あらゆるものが藍色に染められました。明治時代に日本を訪れた外国人は、街に溢れる深く鮮やかな藍色を「ジャパン・ブルー」と呼び、賞賛したと言われています。
藍染の種類
藍染には、主に2つの方法があります。
- 生葉染め:刈り取ったばかりの新鮮な藍の葉をそのまま使って染める方法です。シルクなどの動物性繊維によく染まり、淡く透明感のあるスカイブルーに仕上がります。
- 藍建て:乾燥・発酵させた藍の葉(蒅・すくも)を使い、微生物の力で発酵させて染液を作る方法です。綿や麻などの植物性繊維にも深く濃く染まり、私たちがイメージする「ジャパン・ブルー」の多くはこの方法で染められています。
伝統的な藍染の工程
「藍建て」による伝統的な藍染は、非常に手間と時間がかかる奥深い工程を経て行われます。
- 原料の準備(蒅づくり):夏に収穫したタデ藍の葉を細かく刻み、乾燥させます。その後、水を打ちながら数ヶ月かけて発酵させると、藍の葉は「蒅(すくも)」と呼ばれる染料のもとになります。
- 藍を建てる:大きな甕(かめ)に蒅を入れ、木灰から採った灰汁(あく)や日本酒などを加えて混ぜ、微生物が活動しやすい環境を整えます。適切に管理すると、微生物が働き、水に溶けないインディゴ色素が、水に溶ける「還元型インディゴ(インディゴホワイト)」に変化します。この染液を作る一連の工程を「藍を建てる」と呼びます。
- 染色工程:
- 染めたい布や糸を水に浸けて、染めムラができないようにします。
- 藍甕の中に布を静かに浸し、優しく揉み込みます。染液の中は緑がかった黄色です。
- 引き上げた布を広げると、最初は黄緑色だった布が、空気に触れて酸化することで、みるみるうちに鮮やかな青色に変化していきます。この瞬間は、藍染の最もドラマチックな場面です。
- この「浸けて、空気に晒す」工程を繰り返すことで、色はどんどん濃く、深い藍色になっていきます。
家庭でできる簡易的な藍染
伝統的な方法は難しいですが、現在では家庭でも手軽に藍染を楽しめるキットが販売されています。市販の『天然藍濃縮液』などを使えば、水と混ぜるだけで簡単に染液を作ることができます。
必要な材料:
- 天然藍濃縮液
- 水
- 染めたい布(綿・麻・シルクなどの天然素材)
- バケツ、ゴム手袋など
Tシャツやハンカチなどを、輪ゴムや割り箸で縛って模様を作る「絞り染め」に挑戦するのもおすすめです。自分だけの一点ものが作れる楽しさがあります。
青色作りでよくある質問と解決策
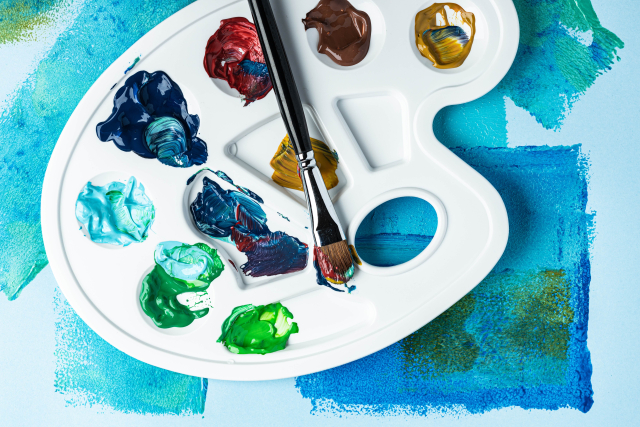
- Q1: 絵の具で混色すると、どうしても色がくすんでしまいます。鮮やかな青は作れませんか?
- A: 色は混ぜれば混ぜるほど、光の反射の波長が複雑になり、彩度が低くなる(くすむ)性質があります。特に、3色以上を混ぜると顕著に濁ります。チューブから出したままの単一顔料の絵の具が最も鮮やかです。混色で鮮やかな青を作るのは限界があるため、もし鮮やかさを最優先するなら、作りたい色に最も近い青色の絵の具(例:セルリアンブルー、フタロシアニンブルーなど)を単体で購入することをお勧めします。
- Q2: 青い食紅が手に入りません。紫キャベツ以外に簡単な代用法はありますか?
- A: もし少量で、甘みがついても問題ない場合は、かき氷シロップの「ブルーハワイ」味が代用品として使えます。液体なので扱いやすく、非常に鮮やかな青色が出ます。ゼリーやドリンクの色付けに便利ですが、風味や糖分が加わることを考慮して使用してください。
- Q3: デジタルで作った青色を印刷したら、全く違う色になってしまいました。なぜですか?
- A: これは、モニター(RGB/光)と印刷物(CMYK/インク)の色の再現方法が根本的に異なるために起こる現象です。特に鮮やかな青は、RGBの色域では表現できても、CMYKの色域では表現できないことが多いです。印刷を前提とするデザインの場合は、必ずCMYKカラーモードでデータを作成するか、あらかじめCMYKに変換して色の変化を確認しながら作業することが失敗を防ぐ鍵です。
まとめ:理想の青色作りへの道

この記事では、絵の具、食紅、デジタル、自然染料という4つの異なるアプローチから、「青色」を作る方法について掘り下げてきました。最後に、成功するための重要なポイントをまとめます。
成功するための重要なポイント
- 目的に応じた方法選択:何のために青色が必要なのかを明確にしましょう。絵画なら絵の具、お菓子作りなら食紅、WebデザインならRGB、染物なら藍染と、目的に最適な方法を選ぶことが第一歩です。
- 材料の品質にこだわる:美しい色を出すには、材料の品質も重要です。発色の良い絵の具、安全性が確認された食紅、適切なカラープロファイル設定など、基本を疎かにしないことが大切です。
- 少しずつ調整する:どの方法においても、色は後から戻せません。焦らず、少しずつ色を加えたり、設定を変えたりしながら、理想の色にじっくりと近づけていくことが成功の鍵です。
青色は、三原色の一つであるがゆえに「無から作り出す」ことが難しい、特別で奥深い色です。しかし、その特性を理解し、目的に合った正しいアプローチを選べば、表現できる青の世界は無限に広がります。ぜひこの記事を参考に、あなたの創作活動や生活の中で、理想の「青」を見つける旅を楽しんでみてください。

