ビジネスメールや挨拶状で「ご高配を賜り」「ご支援賜りますよう」といった表現を目にすることはありませんか?「賜る(たまわる)」という言葉は、相手への深い敬意を示す格式高い表現ですが、その正しい意味や使い方を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
実は「賜る」には大きく分けて2つの意味があり、使い方を誤ると、意図せず相手に不快感を与えてしまう可能性もあります。この記事では、「賜る」の基本的な意味から、類似表現との使い分け、ビジネスシーンで役立つ実践的な例文、そして使用する際の注意点まで、網羅的に解説します。
「賜る」とは?基本的な意味を理解しよう

まずは「賜る」という言葉の根幹となる意味や背景から確認していきましょう。言葉の成り立ちを知ることで、より深く理解できます。
「賜る」の読み方と漢字の成り立ち
「賜る」は「たまわる」と読みます。送り仮名を「たま・わる」と区切りたくなりますが、「たまわ・る」が正しいので注意しましょう。
「賜」という漢字は、部首の「貝」が示すように、もともと財産や宝物を意味していました。そこから、権威ある人から価値あるものを「与えられる」という意味合いを持つようになりました。音読みでは「シ」と発音し、「恩賜(おんし)」や「下賜(かし)」といった熟語で使われます。これらの熟語からも、「目上の人から何かをいただく」という特別なニュアンスが感じ取れます。
謙譲語としての「賜る」:「もらう」の最上級敬語
「賜る」の最も一般的で重要な使い方は、「もらう」を意味する謙譲語です。謙譲語とは、自分や自分の側の立場を低めることで、行為が向かう先の相手を敬う表現方法です。「賜る」は、同じく謙譲語である「いただく」よりもさらに丁寧で、格式高いニュアンスを持ちます。相手からの行為を、特別な恩恵として受け取るという深い感謝の気持ちが込められています。
【謙譲語としての例文】
- 日頃より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。(お客様からの愛顧を「もらっている」ことへの感謝)
- 貴重なご意見を賜り、心より感謝申し上げます。(会議などで意見を「もらった」ことへの感謝)
- 〇〇先生より多大なるご指導を賜りました。(恩師から指導を「してもらった」ことへの敬意)
これらの例文では、相手から受けた物や厚意(ご愛顧、ご意見、ご指導)に対して、最大限の敬意と感謝を示しています。
尊敬語としての「賜る」:「与える」の敬語
実は「賜る」には、もう一つの用法があります。それは「与える」の尊敬語として、身分の高い人が下の者へ何かを与える、授けるという意味で使われるケースです。
【尊敬語としての例文】
- 天皇陛下が〇〇氏に勲章を賜る。(陛下が勲章を「お与えになる」)
- 社長が功労者に感謝状を賜った。(社長が感謝状を「お与えになった」)
ただし、この尊敬語としての用法は、主に皇室関連の報道や、歴史小説、あるいは非常に格式張った式典などで使われるのがほとんどです。現代の一般的なビジネスシーンで「与える」という意味で「賜る」を使うことはまずありません。ビジネスパーソンとしては、まず謙譲語としての使い方をマスターすることが重要です。
「賜る」と「承る」の違いを正しく理解する
「賜る(たまわる)」と「承る(うけたまわる)」は、読み方も似ており混同しやすい言葉ですが、意味と使い方は明確に異なります。この違いを理解することが、正しい敬語表現への第一歩です。
「承る」の意味と使い方
「承る」は、「聞く」「引き受ける」「伝え聞く」の謙譲語です。相手の依頼や注文、意見などを謹んで引き受けたり、聞いたりする際に使います。行為そのものに焦点が当たっているのが特徴です。
【「承る」の例文】
- この度はご注文いただきありがとうございます。確かに承りました。
- ご依頼の件、承知いたしました。早速、手配いたします。
- あいにく担当は席を外しております。よろしければご用件を承ります。
使い分けの決定的なポイント
「賜る」と「承る」の最も大きな違いは、「承る」は具体的な品物に対しては使用できないという点です。「承る」はあくまで依頼や用件といった「事柄」を引き受けるときに使う言葉です。
| 表現 | 正しい例 | 間違った例 |
|---|---|---|
| 賜る | ○ 記念品を賜りました | × ご用件を賜りました |
| 承る | ○ ご用件を承ります | × 記念品を承りました |
【使い分けのルール】
- 物や厚意・恩恵を「もらった」とき → 「賜る」
- 依頼や注文、用件を「引き受けた・聞いた」とき → 「承る」
「プレゼントを承りました」や「ご厚情を承りまして」といった表現は誤りです。この場合は「プレゼントをいただきました」「ご厚情を賜りまして」とするのが適切です。
「賜る」と「いただく」の違い|どう使い分ける?
同じく「もらう」の謙譲語である「いただく」と「賜る」は、どのように使い分ければ良いのでしょうか。どちらもビジネスシーンで頻繁に使われるだけに、そのニュアンスの違いを理解しておくことが大切です。
丁寧さと格式のレベル
両者の違いは、相手への敬意の度合いと表現の硬さにあります。丁寧さのレベルは以下のようになります。
もらう < いただく < 賜る
「賜る」は「いただく」よりもさらに丁寧で、公的・儀礼的な響きを持つ言葉です。そのため、日常的なコミュニケーションで使うと、やや大げさに聞こえてしまうことがあります。「賜る」は、文書や改まった場面での使用が基本と心得ておきましょう。
シーン別の使い分け目安
具体的なシーンに応じて、どちらの表現がより適切かを見ていきましょう。
| シーン | おすすめの表現 | ポイント |
|---|---|---|
| 日常的なビジネスメール・会話 | いただく | 「資料をいただきました」「アドバイスをいただきありがとうございます」など、日常業務では「いただく」が自然です。 |
| 社外向けの公式文書・挨拶状 | 賜る | 企業の公式な通知や、年賀状、お礼状などでは「ご高配を賜り」「ご支援を賜り」といった表現が適切です。 |
| 結婚式や式典のスピーチ | 賜る | フォーマルな場での挨拶では「ご祝辞を賜り」「ご臨席を賜り」など、格式高い「賜る」がふさわしいです。 |
| 親しい上司とのやり取り | いただく | 関係性が近い相手に「賜る」を使うと、かえって距離感を感じさせてしまう可能性があります。「いただく」が適切です。 |
| 重要な契約や多大な恩恵への感謝 | 賜る | 特に大きな契約をいただいた際のお礼状などで、「この度は格別のご用命を賜り…」のように使うと、深い感謝の意が伝わります。 |
基本的には、日常業務では「いただく」、改まった場面や深い感謝を示す際には「賜る」と使い分けるのが良いでしょう。
「賜る」の正しい使い方|シーン別の例文を紹介

ここからは、実際のビジネスシーン別に「賜る」の具体的な使い方を豊富な例文とともに見ていきましょう。定型表現として覚えておくと非常に便利です。
ビジネスメールで頻出する定型表現
ビジネスメール、特にお客様や取引先へのメールでは、「賜る」を使った定型表現が挨拶や結びの言葉として頻繁に用いられます。
1. 日頃のお礼を伝えるとき(書き出し)
- 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 日頃より一方ならぬご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
- この度の成功は、ひとえに皆様のご支援を賜りました賜物と深く感謝しております。
※「ご高配」は「相手からの配慮や気遣い」を意味する敬語です。
2. 協力や支援をお願いするとき(結び)
- 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
- 何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
- 引き続きご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
※「ご鞭撻」は「努力するように励ます」という意味で、指導を乞う際にセットで使われます。
3. 相手に意見や助言をお願いするとき
- 本件につきまして、忌憚のないご意見を賜りたく存じます。
- 先生のご見識によるご指導を賜れれば幸いです。
- 皆様からの貴重なご意見を賜りますよう、お願い申し上げます。
文書・挨拶状での使い方
お知らせやお詫び、お礼状といった改まった文書でも「賜る」は重要な役割を果たします。
【案内状の例】
この度、弊社は下記住所へ移転する運びとなりました。これを機に、社員一同心を新たにして業務に精励する所存でございますので、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【お詫び文の例】
この度は弊社の不手際により、多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご容赦を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
【お礼状の例】
先日はご多用の中、貴重なお時間を賜り、誠にありがとうございました。また、その折に賜りましたご厚情に対し、心より御礼申し上げます。
スピーチや式典での使い方
結婚式や記念式典など、公の場でのスピーチでは、格式高い「賜る」が非常に効果的です。
【結婚式のスピーチ】
- 本日はご多用の中、私たちのためにご列席を賜り、誠にありがとうございます。
- 皆様から温かいお祝いのお言葉を賜り、胸がいっぱいでございます。
- 未熟な二人ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【式典の挨拶】
- 本日はお忙しい中、記念式典にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。
- 今日のこの日を迎えられましたのも、ひとえに皆様方のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。
「賜る」を使う際の注意点
「賜る」は非常に丁寧な表現だからこそ、使い方を間違えると意図が正しく伝わらないばかりか、かえって失礼な印象を与えてしまうこともあります。注意すべき点をしっかり押さえましょう。
1. 多用は避けるべき理由
一つの文章の中で「賜る」を何度も繰り返して使うのは避けましょう。丁寧な言葉であっても、使いすぎると文章がくどくなり、仰々しい印象を与えてしまいます。その結果、かえって感謝の気持ちが薄れて伝わってしまう可能性があります。このような状態を「慇懃無礼(いんぎんぶれい)」と言い、丁寧すぎることがかえって無礼になる典型例です。
【NG例(多用しすぎ)】
先日はお時間を賜り、貴重なご意見を賜り、また資料も賜りまして、誠にありがとうございました。今後ともご指導を賜りますよう、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【OK例(適度な使用)】
先日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。その際に賜りましたご意見は、今後の事業計画に活かしてまいります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
上記OK例のように、「いただく」や「頂戴する」といった他の謙譲語と織り交ぜることで、自然で品のある文章になります。
2. 使う相手・シーンを慎重に選ぶ
たとえ役職や年齢が上の人であっても、日常的に接する直属の上司など、心理的な距離が近い相手に「賜る」を使うと違和感を与えることがあります。「よそよそしい」「皮肉を言っているようだ」とネガティブに受け取られかねません。
【使用を避けるべきシーン】
- 日常的な業務報告(例:「部長、先ほどの資料、賜りました」)
- 親しい上司とのカジュアルな会話
- 同僚や後輩とのコミュニケーション
相手との関係性や状況を考慮し、TPOに合わせた言葉選びが重要です。
3. やってはいけない!よくある間違い
敬語の使い分けで起こりがちな典型的な間違いをまとめました。
- 物に対して「承る」を使う
(誤)記念品を承りました → (正)記念品を賜りました/いただきました - 自分の行為に使う
(誤)私が部下にお菓子を賜りました → (正)私が部下にお菓子を渡しました/あげました - 目下の人からの行為に使う
(誤)後輩からアドバイスを賜りました → (正)後輩からアドバイスをもらいました
「賜る」は、あくまで目上から何かをいただく際に使う謙譲語であることを忘れないようにしましょう。
「賜る」に関するQ&A
ここでは、「賜る」の使い方に関して、特に判断に迷いやすいケースをQ&A形式で解説します。
- Q1. 直属の上司へのメールで「ご指導賜りありがとうございます」は使えますか?
- A1. 関係性によりますが、基本的には「ご指導いただきありがとうございます」の方が自然です。「賜る」を使うと少し堅苦しく、距離感のある印象を与える可能性があります。ただし、非常に重要なプロジェクトで多大なサポートを受けた際のお礼メールなど、特に感謝を強調したい場面で一度だけ使うのは効果的です。
- Q2. 取引先からのメール返信で「資料、賜りました」と書くのはおかしいですか?
- A2. 文法的には間違いではありませんが、やや古風で硬い印象を与えます。現代のビジネスメールでは「資料を拝受いたしました」や「資料、ありがたく拝見します」といった表現の方が一般的でスムーズです。特に感謝を伝えたい場合は「早速のご送付、誠にありがとうございます。頂戴した資料は、部内で共有させていただきます」のように表現するのが良いでしょう。
- Q3. 「賜りますよう」と「いただけますよう」はどう使い分ければいいですか?
- A3. 依頼する内容の重要度や相手との関係性で使い分けます。社外の顧客や取引先への公式な依頼、例えば契約内容の確認や規約への同意を求めるような文書では「ご確認を賜りますようお願い申し上げます」が適しています。一方、社内の上司や他部署への一般的な依頼であれば「ご確認いただけますようお願い申し上げます」の方が柔らかく、適切な表現です。
「賜る」の類語・言い換え表現
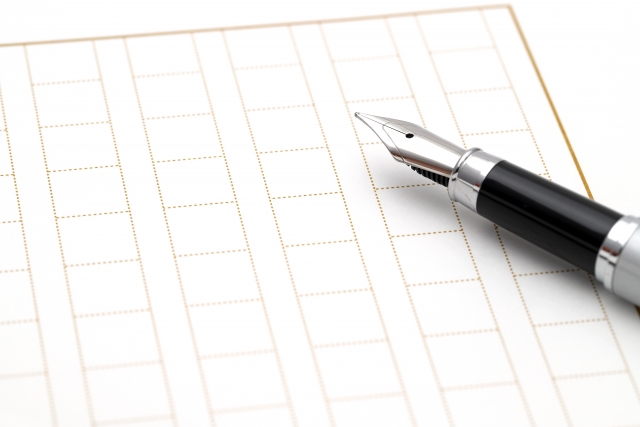
「賜る」は格式高い表現だからこそ、シーンに応じて他の言葉に言い換える柔軟性も必要です。
謙譲語としての言い換え
「賜る」と同様に「もらう」の謙譲語として使える言葉です。
- いただく:最も一般的で、口頭でも書き言葉でも幅広く使える表現。
- 頂戴する:「いただく」よりも少し改まった表現。金品や価値あるものを受け取る際に使われることが多い。
- 拝受する:「謹んで受ける」という意味の非常に硬い表現。主にメールや文書で、書類などを受け取ったことを相手に伝える際に使う。「拝受いたしました」は定型句。
- 授かる:神仏や非常に身分の高い人から、特別なもの(命、賞、知恵など)を与えられるという意味で、ビジネスシーンでの使用は限定的。
尊敬語としての言い換え
「与える」の尊敬語としての「賜る」は、現代ではほとんど使われませんが、言い換える場合は以下のようになります。
- くださる:最も一般的な「与える」の尊敬語。「社長が資料をくださった」など。
- お与えになる:「くださる」よりもさらに敬意の高い表現。「会長が記念品をお与えになった」など。
「賜る」の送り仮名|「賜る」と「賜わる」はどちらが正しい?
パソコンなどで「たまわる」と入力すると、「賜る」と「賜わる」の両方が変換候補に出てくることがあります。どちらを使うべきか迷うかもしれませんが、文化庁が示す「送り仮名の付け方」において、以下のように定められています。
- 原則: 賜る(たまわ・る)
- 許容: 賜わる(たまわ・る)
「賜わる」も間違いではありませんが、公的な文書やビジネスシーンでは、本則である「賜る」を使うのが一般的であり、無難です。迷った場合は「賜る」と覚えておきましょう。
まとめ

「賜る」は、相手への深い敬意と感謝を示す、非常に格式高い敬語表現です。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- 基本の意味:謙譲語としては「もらう」の最上級表現。尊敬語としては「与える」を意味するが、現代での使用は稀。
- 他の敬語との違い:「承る」は依頼や用件に使い、物には使えない。「いただく」よりも「賜る」の方が丁寧で格式が高い。
- 使うべきシーン:社外向けの公式文書、挨拶状、お礼状、そして結婚式や式典などのフォーマルな場。
- 注意点:多用は避け、「いただく」などと使い分ける。親しい上司や日常業務では使わない方が無難。
- 送り仮名:「賜る」が原則(「賜わる」も許容)。
「賜る」を正しく使いこなすことができれば、あなたの言葉遣いはより洗練され、ビジネスにおける信頼性も向上するでしょう。しかし、その格式の高さゆえに、使う場面を慎重に見極めることが何よりも大切です。状況に応じて適切な表現を柔軟に使い分けることで、円滑で質の高いコミュニケーションを実現してください。

